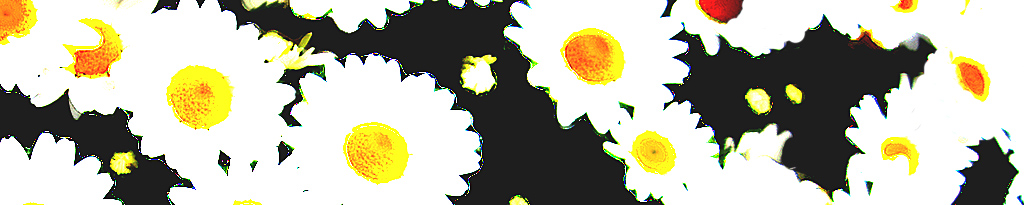
|
目を開けると其処は、白い部屋だった。私の体は、ベッドの上だった。けっして、ふかふかと気持ちの良い寝心地ではなかったけれど、体を休めるには適当な其れだった。さて自分はどうして、此処に寝ているのだろう、だとか、此処は一体何処なのだろう、だとか。少し考えれば判ることなのだけれど、咄嗟には浮かばなかった。ただぼんやりとした意識を天井に向けていた所、ふ、と聞き慣れた声が私の耳に入る。 「お目覚めかい?」 その凛とした声を、他の誰かと聞き間違える筈が無かった。私は思わず勢い良く上半身をベッドから引き剥がし、声のした方へ体を向ける。其処には、パイプ椅子に座って居る、あの人の姿が在った。その姿を見た瞬間、全てを思い出す。そうだ、此処は、探偵社の医務室。いつもあの人が怪我人を寝かせる所。私ははっとして、自分の体を服の上からぺたぺたと触る。痛い所は無い。だけどそれはきっと「怪我なんてしていない」じゃなくって、「怪我の痕など残していない」と云うのが正しい。顔を上げ、改めて、その人と目を合わせる。彼女は薄く唇を開くと、私の名前を呼んだ。、と。その声で呼ばれる度に、嗚呼私の名前はこんなにも美しい響きをしていたのか、といつも胸が震える。 「…与謝野、先生」 「顔色は悪く無さそうだねェ」 「先生、あの…私…」 意識を失って此処へ運ばれる前の出来事を、覚えていない訳では無かった。今日は前から先生と「出掛けよう」と約束していた日で、私は先生と過ごせる事が嬉しくって嬉しくって浮かれていた。戦闘要員ではないにしろ、武装探偵社に身を置いて貰っている限り、常に危険と隣り合わせに生きているという自覚を、持っていなくてはならなかったのに。一つ依頼を解決すれば、一つ何処かで恨みを買うような、そんな仕事だ。つい先日も密輸組織とのいざこざがあったばかり。逆恨みされる事なんてしょっちゅうだ。どうにか恨みを晴らしてやろうっていう連中が、探偵社の周囲を探っている中で、「女二人」が浮かれた様子で出てきたとすれば?…これはもう、その機を逃す訳にはいかないと、相手方も思ったのだろう。 直接危害を加えるつもりだったのか、ただ脅して捕らえて人質にしてしまおうというつもりだったのか、今となっては分からないし、私にとってはどうでもいい事だった。どうでもよくない事と言えば、相手が先ず、私ではなく与謝野先生の背後を狙った、という事だ。先生はお強い。だけどあまり前線に出る役目では無い。だって先生の何よりの仕事は怪我の絶えない社員さん達の治療だから。…だから、先生の実力を知らず、只の、非力な事務員か何かと勘違いして、襲ったのだと思う。先生が咄嗟に反応できないような不意打ちを狙ったのだ。私は、先生の背後に怪しい男を見た瞬間、頭がぱっ、と真っ白になり、「危ない!」と叫んだ。男が先生へ刃物を向けるのと同時にその巨体に飛び掛かる。なんとかそのナイフを取り上げようという考えで頭がいっぱいになり、揉み合いになった末、ぐさり、と鋭利な刃先が皮膚を突き破る音を確かに聞いた。直後広がる激痛に、安堵したのだ。嗚呼、良かった、刺されたのは先生でなく私なのだと。――私の記憶は、そこで終わっている。意識を完全に手放す直前、先生が私を呼ぶ声を、遠くに聞いた気がするけれど。 「先生っ、あの後どうなったんです、私、何にも考えずに飛び掛かってしまったけれど、敵の数が一人だなんて限らないですよね、もし人質として攫う目的であれば、此方を囲む位の、複数人を用意する筈…」 「そうだねェ…アンタを刺した奴以外に三・四人は隠れてたさ。一人が地面に転がるのを見てすぐに姿を現したけどね」 「そんな…、じゃあ先生はあの後、複数人相手に…。お怪我は!?」 「ハッ、何云ってンだい。たったあれだけの数」 「え…ぜ、全員、お一人で倒したのですか…?」 「当たり前の事訊くンじゃないよ。場数が違うのさ。まあ、骨の無い奴らだったね」 腕を組み、ふん、と当然のことのように鼻を鳴らしてみせる与謝野先生を見て、安心…というより、脱力してしまう。そうだ、分かってたはずじゃないか。先生はお強い。私なんかが動かなくっても、あの程度の敵、一人でどうにかなさっていたんだ。私の力じゃ、たった一人の敵だって倒せないのに。へなへなと力無く肩を落とす私を、先生の少し不機嫌そうな「」という声がはっとさせた。慌てて背筋を伸ばして先生のお顔を見る。表面上では分かりにくいけれど少しむっとしているように感じて、私はびくびくしながら、「はい」と返事をした。 「妾に云う事があるだろう?」 怒っている。矢っ張り怒っている声だ。薄く微笑みながらも、声が冷たい。当然ながら先生の求めている言葉は、「御免なさい」だと思う。だって、怒っているのだもの。怒っている人には先ず、何がどう在ってもとにかく謝らなくっちゃいけない。私はベッドの上でいそいそと正座をすると、先生と向き合い、そうして深々と頭を下げた。 「先生の手を煩わせてしまって御免なさい。先生は命の恩人です。怪我を治してくださって有難う御座います」 「それで?」 「…それとその…御迷惑を…」 続きを求められるとは思っていなくて、その先がしどろもどろになる。それでも先生は未だ、「では許そう」と云ってはくれない。依然、不機嫌そうな様子のままだった。私が、先生にしてしまった事、とは。無闇に突っ込んで、結果的に先生の厄介を増やしてしまった事?だって怪我を負った私を治す事も、気を失った私を此処まで運ぶ事も、私が勝手に飛び出さなければ済んだ事だ。だって、飛び出さなくとも、私が何かをしなくても、先生は一人で、解決していた。その麗しい容姿で油断させて、男達を次から次へと倒す様子が目に浮かぶ。…そう、きっと、謝るべきことは、「それ」なのだけれど、口にしてしまえば、自分が酷く哀しい気持ちになるという事を、判っていた。だから出来れば云わずに見逃してもらいたかった。だけど、真っ直ぐに此方を見据える瞳が、そんな逃げ道を塞いでいる。小さく息を吐くと、私は、視線を落とし、掠れた声で、呟く。 「…、…余計な、事を…して、御免なさい…」 「全くだ。あんな莫迦な真似、二度とするンじゃないよ」 心臓を握り潰されるような痛みが走る。きゅ、と握った拳が震えた。ぴしゃりと言い切った与謝野先生の声は冷たい。私が、先生を助けたくってしたことは、「余計な事」で、「莫迦な真似」だ。認めてしまったら辛くなるって判っていたけれど、こんなに胸が痛むとは。自分の言葉で言い聞かせ、先生にも念を押され、なんだか涙が出そうになる。心の何処かで、喜んでもらえるかもしれないと期待でもしていたんだろうか。 ふと顔を上げると、先生は視線を私から逸らしていた。そのツンとした様子に、胸がざわざわと落ち着かなくなる。怒ってらっしゃる。もう、どれだけ謝ろうとも、許してもらえないかもしれない。もう、完全に、失望されたかもしれない。嫌われたらどうしよう、もうお前なんて何処かに行ってしまえと云われたらどうしよう。そう考えるとさあっと恐ろしくなって、私は思わず「先生!」と縋るように叫んでいた。言い訳だと判っていても、どうにか、私の気持ちを判ってほしかった。 「あの、私、先生が危ないって思ったら、じっとしていられなくて…私、わたし、先生を守れたらって…お役に立てたら、って…」 「それが余計だッて云ってるんだ!」 自分の言葉を遮った先生の声が、心底苛立った様な声で、私はびくっと身を震わせる。そうして呆然としながらも、じわじわと込み上げてくるものを感じて、いけない、いけない、堪えなくては、と必死に自分自身に言い聞かせるのに、気付いた時にはぽろぽろと涙が溢れて、両手で顔を覆った。いつも、思っていた事だ。先生の役に立ちたい。先生を守れる位に強くなりたい。私はちっとも自分の体に傷が付く事なんて怖くなかった。ナイフを持った巨漢にも、凶悪な兵器を持った軍隊にも、先生の危機ならば、何も恐れず突っ込んでしまうだろう。それ位の気持ちが、私にはある。だけどそんな気持ちさえ、先生にとっては迷惑だったんだ。余計な事だ。私なんかに、守られるなんてまっぴらなんだ。 「…ごめ、…なさい…、先生……」 涙ながらに必死に何度も「御免なさい」を唱えていると、そんな私に呆れたのか、部屋に先生の大きな溜息が響く。顔を覆っている私は先生の様子を確認できないけれど、続いてガタンと椅子から立ち上がる音がして、私は心臓が止まりそうになった。行ってしまう。こんな私を見捨てて、先生が、行ってしまう。「いかないで」と唱えようとした口からは言葉にならない嗚咽しか出てこなかった。泣き止まなくちゃ、とそう思うのに、思えば思うほど悲しくなって涙は溢れてくる。どうして私はこうも駄目なのだろう。先生のお傍に居たいのに。 哀しい気持ちいっぱいだったけれど、ドアの向こうに先生が行ってしまう音は、なかなか聞こえてこない。不思議に思ったその直後、ふ、と何かあたたかなものが私に触れた。かと、思えば、そのぬくもりが、ぎゅう、と私を抱きしめた。突然の事に、すぐには何が起こったのか理解出来ない。だけどこの部屋に、今、先生以外誰も居ないのだ。ベッドの上に座り込んでいる私を、先生が近づいて来て、自分の胸に抱き寄せた、なんて、すぐには信じられない。 「…莫迦な子だねえ、アンタは」 「せん、せい…」 「もうあんな無茶するんじゃないよ」 「……、…先生…?」 「アンタの怪我を治すのは骨が折れるんだ」 ぴったりとくっついた、零の距離で聞こえたその声は、思いの外穏やかで、それでいて少し、弱々しい。私の怪我を治すのは、他の人の怪我を治すよりも労力が要る、のか。すん、と鼻を啜って、小さく「どうして?」と尋ねる。すると、先生は一度体を離し、私の肩に手を置いて、少しだけ屈んで、こつんと額を合わせた。鼻と鼻とが触れる様な近さで、先生が悪戯っぽく、笑ってみせる。そのお顔があんまりにも、可憐で、私の心臓を脅かしてならない。とくんと胸がときめく音を聞いていると、さらに先生は、こんなことを言う。 「さァてね。どうしてだと思う?」 「…えぇと…」 「他の誰にもそんな事は思わないのに、アンタの怪我だけは、治したくないんだよ」 「そ、そんな…!哀しいです…そんなに治したくないのですか…!」 「ああ、そうさ」 さらりと言い切られて、私はこれでもかと云う程衝撃を受けるけれど、どうも今の先生は怒っているわけではない。私の、「そんな…!」と狼狽える様子を見て、満足そうに、にやりとしている。私を嫌って云っているのではなく、からかって、意地悪を云っている様な、そんな風に思えた。けれど私としては、混乱してしまう。先生が能力を遣う事を嫌がるなんて、なかなか無いはずだ。普段ならむしろ、必要以上に使いたがる。いつも社員さん達に「どっか怪我してないかい」と聞いて、治療は必要ないと言われれば小さく舌打ちしているのだし。私は先生のお役になかなか立てないけれど、先生が誰かを治療したくて堪らないときに体を差し出す事くらいなら出来ると思っていた。なんと、其れさえも御迷惑だなんて!私は先生の為に他に何が出来るというんだろう…。考えて落ち込んでいると、先生は微笑んで、私の頭をくしゃりと撫でた。途端に、きゅう、と心臓が啼く。先生のお陰で、私の心臓はいつも忙しい。 「いいかい?。そう云う事だから、アンタは、危ない事なんてするンじゃないよ。かすり傷一つだって許してやらないからね。妾に二度とアンタの為に能力を使わせない事」 「せ…先生、本当に本当に、嫌なんですね…私を治す事が」 「勿論」 「……ど、どうして私だけ…?」 「自分で考えな。判る迄はせいぜい怪我と病気に気を付けて、妾の傍についていればいいさ。それが、アンタが妾の為に出来る事だろう?」 そう。先生が私の為に能力を遣うのを嫌がるのだったら、遣わないで済むように、私が怪我をしないように気を付ければいい。今回の様な無茶はしないで、大人しく先生に、守られていればいい。理屈は判るけれど、「でも…」と渋ると、先生がむっとした表情で、「でもじゃない。返事は"はい"だよ」と叱りつける。慌てて「はい!」と背筋を伸ばすけれど、どうしても、矢っ張り、納得がいかない。嫌われている訳ではないのなら、どうしてそんなに、私を治す事を嫌がるのだろう。いくら訊いてもきっと、「自分で考えろ」と云われてしまうのだろうけれど。 「……」 諦めて私が小さく溜息を吐くと、与謝野先生がベッドの端に腰を下ろし、こちらの顔を覗きこんできた。何かを確かめるように、じぃ、と。綺麗な瞳に見つめられて、ぽっ、と染まる私の頬を、細い指が撫でる。祈るように優しく。あんまりにも優しい手つきなので、自分が壊れ物か何かになってしまったんじゃないかって錯覚しそうになる。何か云おうって思うのに、其れと同時に、この沈黙が、とても尊い時間に思えて、私は声を出せずにいた。ふ、と先生が目を細めたその様子に、胸が切なくなる。どうしてだろう、悲しげに、見えた。 先生、先生、大丈夫ですよ。私、強くないけど、だけど、そんなに脆くないの。先生がいてくれるなら、きっと、ずっと。 「…妾の傍から居なくなるンじゃないよ。絶対に」 |
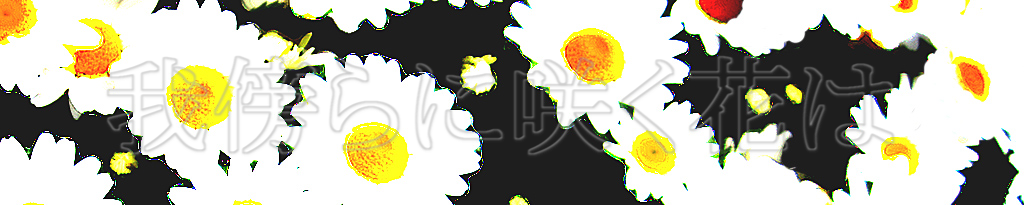
|
「治療したくない、なんて云い方じゃあんまりでしょう。先生が嫌なのは、彼女を治す事じゃない。能力を遣う為に彼女を瀕死に追いやる事、なんだから」 与謝野が医務室の扉を開けて廊下に顔を出すと、壁に背をもたれた太宰がそう声を掛けてきた。目が合うと、へらりと軽く笑ってみせる。いつから部屋の中の会話を聞いていたというのか。呆れたように溜息を吐いて、与謝野は後ろ手に医務室のドアを閉めた。なるべく音を立てないようにそっと。疲れていたらしく、は医務室のベッドでまた眠ってしまった。それを起こさないように、という与謝野の配慮だった。 「盗み聞きとは悪趣味だねェ」 「様子が気になって見に来たら、中に入れなかったので。空気的に」 「おや、御邪魔虫の自覚が有るンだったら話は早い。さァ、仕事に戻った戻った」 ぱたぱたと手で追い払う仕草に、太宰は肩を竦める。それでも、口を動かす事は止めなかった。 「大事なんですね。治療の為とは云え、その体を傷付ける事を躊躇う位に」 そう、其れこそが、与謝野がに能力を使いたくない理由だ。いつもなら、鉈でも鋸でもチェーンソーでも持ち出して、意気揚々と患者を「解体」する与謝野だけれど、の体を傷付ける事は気乗りしない。瀕死の状態の彼女が目の前に転がされれば、何の躊躇いも無く能力を遣うだろう。けれど、深手であっても「瀕死」と呼べない怪我のが目の前に現れたなら、話は違う。与謝野の能力の発動条件は、対象が瀕死の状態である事。そうで無い場合、瀕死に至る迄の手を加えなくてはならない。どうせ、すぐに治す。治せる傷だ。治せない傷など無い。それは判っている筈なのに、理屈ではどうにもならない所で、ただただ、「嫌だ」と思うのだ。与謝野は罰が悪そうに口を尖らせたまま視線を逸らすけれど、太宰は更に話を続ける。すらすらと推理を言い当てる乱歩の様に、なんでも御見通しだと言わんばかりだ。 「それに"治療したくないから"じゃなく、素直に"心配だから危ない事をしてほしくない"って云えばいいのに」 「…フン、気付かないなら気付かないままでいいンだよ。わざわざ説明してやる気は無いね」 「やれやれ…敵は与謝野先生が全員撃退したそうですけど…彼女を背負って与謝野先生が帰って来た時、皆驚いていましたよ。敦くんなんて特に。"あんな与謝野さん初めて見ました"ってね」 自分を庇おうと、刃物を持った男にが飛び掛かった時、頭が真っ白になった。揉み合う内にが刺されて、心臓が止まりそうになった。与謝野はその時の事を思い出して、ぐっ、と拳を握る。には、涼しい顔をして余裕で敵を倒した風に話したけれど、実際には、余裕なんて微塵も無かった。ただカッとなって、手当たり次第敵を蹴散らした。殺す気が無かったのかと訊かれれば、答えられない位に。だから探偵社に戻った与謝野の顔を見るなり敦は「あんなに怒った様子初めて見た」と云ったのだ。怒らない筈がない。大事なに危害を加えられて、頭に血が上っていた。 敵に隙を見せて、にあんな行動を取らせてしまった自分に何より苛立つけれど、もう一つ。意識を取り戻すや否や「先生は無事だったのですか」と他人の心配をして、自分の行動に何の反省もしていない様子のに、腹が立った。だから冷たく、きつく言い聞かせたのだ。二度とするな、と。は「怪我をしても先生が治してくれるから大丈夫」という考えではなく、「先生の為なら死んだっていい」と、そういう考えだった。ぞっとする、そんな考え。 「そんなの、妾の為になるもんか。……死んだら治せないんだ。妾は、が無事で居てくれれば、それでいい」 ぽつり、と零れた与謝野の独り言に、太宰は薄く微笑む。彼女の、本心なのだろう。せっかくなら当人に直接、素直に、云ってあげたらいいのに。いや、いっそ自分が。「与謝野先生は、君が心配で仕方が無いんだよ。君が危ない目に遭う事が何より嫌なんだ。無事でいてほしいのだよ。怪我一つなく、無事で」――そう、本人に伝えられたらいいのだけれど、きっとこの様子じゃあ、与謝野にとって余計なお世話なのだろう。乱歩の様な推理力が無くたって、身近な者は、傍で見ているだけで判る。二人はお互いがとても大切なのだ。お互いが思っている以上に。は役に立ちたい役に立ちたいといつも思っているけれど、何より与謝野の為になる事と云うのは、矢っ張り、自身が無事で居てくれる事、なのだ。傍に居てくれる事。ただ、それだけ。 「…傍に居ないと堪えられないのは、与謝野先生の方かもしれない」 そう呟くと、死にたがりの太宰は背を向けて、廊下を歩き出した。「死なせたくない」なんて、自殺嗜癖で心中願望のある彼とは無縁の感情なのかもしれない。けれどきっと世間的に見て、自分のそれより自然で、綺麗で、素晴らしい感情なのだと云うのは、理解している。歩いて、歩いて、与謝野の目の届かない所までやって来ると、太宰は小さく笑った。あの二人がお互いに抱いている感情が、同じ種類の「愛しい」かは判らないけれど、きっと、判らないままが一番善いのだろう。周囲には。否、ひょっとすると、本人達にとっても。 残された与謝野は、医務室の扉を振り返る。もう一度だけその扉を開き、の健やかな寝息を聞いて安心を得たい所だったけれど、いぃや、矢っ張り、とすぐに正面へ向き直った。 今日は少し、弱い所を見せすぎた。強い自分で在ろう、の傍では。あの娘が「守ってあげたい」だなんて莫迦な事思わない位に。あの娘が「ついていきたい」と思い続けられる位に。 死ぬ理由になんてなってやらない。妾はあの娘の生きる理由で在り続けよう。 |