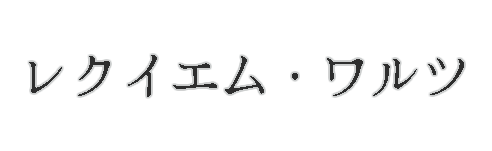でもきっとそうなのだからしかたない。最初にその言葉を口にしたのはどこの誰なんだろう。どんな関係のどんな相手を思ってどんな気持ちで言ったのだろう。どれほどの無念と悲しみのこもった言葉なのか、考える。きっと私には計り知れない感情なのだろうに、顔も名前も知らない誰かに同情して、いつの間にかその誰かの顔は自分の顔をしていて、私の声で言うのだ。「死んだ人間には敵わない」。諦めや自嘲のにじむその声が酷く不愉快で、何に対してなのかもはっきりしない悔しさが胸の中に渦巻いていた。
「コーちゃん」
言いたい言葉があった。でも全部ぐっとこらえて、彼の名前を呼ぶだけにとどめた。とどめたつもりだったのに。
私が声をかけたところで、私に背を見せている彼がこちらを向くことはなかった。コーちゃんの視線は、この狭い部屋の中、テレビに釘付けだ。いや、釘付けといっていいのかもわからない。どんな表情でそれを見ているのかはわからない。ぼんやりと見ているのかもしれないし、食い入るように見ているのかもしれない。ただ、私の声は聞こえていない。たまにあるのだ。こういうときが。わかっているのだ。わかっているのに。
そんな様子の彼を見ていると、先ほど押しとどめたはずの言葉が、外に出たくてじわじわと私の喉元までせり上がってくる。私はテレビの中の、ニュースを読み上げるアナウンサーの声に被せてそれを口にした。遮るための目的で。こっちを向いてよと言う意図で。
『――自殺と見られており、発見された女性の……』
「私も死んだらコーちゃんの忘れられない女の子になれるのかな」
コーちゃんがこっちを見た。首を動かすその速さが尋常じゃなくて、バッ!って効果音がついてて、笑うところじゃないのにその勢いに少し、ふっ、となる。ごめんね。
目が合って、何を言うわけでもなくしばらくコーちゃんはジッと、私の顔を見た。私の言葉の意図を探るように、なのかもしれないけれど、たぶん探らなくったってなんとなく彼は分かっている。私の中の仄暗いものを、コーちゃんは分かっている。
やがて彼の唇がひらく。何か言いかけただろうに、その声はただ、つとめて優しく私の名前を呼んだ。それすらなんだか、はぐらかされる前触れのようで私は落ち着かなかった。悔しかったとも言う。
「ちゃん」
「後悔してる?『あの子』のことを知ってる私を、いまだに傍に置いてること」
「そんな。後悔なんてしてないよ」
「本当に?」
「本当さ。だってボクはちゃんとこうしていられることが」
「でも私かなわない気がするんだ。『あの子』に。あの子はこの先もコーちゃんの胸の中にずっといるんだろうなって思うよ」
「……」
「べつに、コーちゃんがあの子のこと心底愛してたわけじゃないと思うけどさ。むしろ愛してあげられなかったことに後悔がくっついてそうだし。だからヤキモチってわけじゃないよ。いや、ヤキモチっぽい感じはするけど、そういう意味じゃなくて、ただ、ずるいなって」
「…………」
「死んだら永遠になるって、よくいうでしょ。あの子だってきっと、コーちゃんの」
「後悔してる?『あの子』の話を聞いたこと。こんなボクの傍にいること」
「まねしないでよ」
コーちゃんが笑う。はは、ごめん、って。困ったように笑う。それから、笑うのをふっとやめて私に言った。「やめてほしいな。そういうふうに言うの」
「ボクに愛されるために死んでやる、って言われてるみたい」
「そう言ったもん」
「やめてよ」
「だって」
「本当にやめてね」
「怒ったの?」と聞く自分の声に、べつに怯えも戸惑いもなかった。それがコーちゃんも分かっているようで、あきれたようにわざとらしく、は~っと大きく溜息を吐いた。
「あのねえ」
「だって、コーちゃんの記憶の中にずっといるんだよ、あの子」
「キミだっているよ」
「でも記憶の中のあの子には勝てないよ」
「どうしてそう思うのさ」
「だって、死んじゃったらさ、変わらないんだよ。記憶の中で綺麗なままだし。見た目も、気持ちも。喧嘩もしないから嫌いになることが今後全然無いし、見た目も歳とらない若くて可愛いままだし、忘れられることだってない、いや顔や声を忘れたって、存在を、忘れないでしょ、コーちゃん」
ああなんてめんどくさい女なんだろうな、最低な人間なんだろうな、と自分でも思った。自分の口から飛び出す言葉すべてに軽蔑した。死んだあの子には理由があって、追い詰められるまでの苦しさがあって、決して「いいなあ」なんて不謹慎なことを言うべきではないのだ。うらやましいなー私も死んじゃおっかなーなんて、最悪な発言だ。
私は正直に言えば、コーちゃんに怒ってほしかった。それはもうぶちぎれて、見たことも無いくらいの鬼の形相で私の襟首をつかんで引きずりまわして「そんなに死にてーなら殺してやる!」と包丁で刺してほしかった。正直に言うなら。きっとそうすれば特別だ、コーちゃんの忘れられない存在になれる。そう考えた。
でもコーちゃんはそうしない。「そっか」と一度ちいさく呟いて、しばらく黙って、テレビを消した。交際相手とのトラブルでなんやかんやあり最終的に自殺に追いやられた気の毒な女の子のニュースは、私たちには聞こえなくなった。
「コーちゃん」
「なあに」
いざテレビが消えて静かになって、コーちゃんに見つめられると、それはそれで落ち着かなかった。今からコーちゃんが豹変して私を引きずり回す可能性もゼロじゃないと思ったら、やっぱりそれはそれで心臓がバクバク音を立てた。ぜんぜん、ふつーに怖い。怖いんだ。ずっと、いつも、本当は。
「私のこと嫌いになった?」
「なってないよ。これからなるかもしれないけど、今はなってない」
「これからなるかもしれないんだ?」
「だってキミは生きてるだろ」
喉がきゅっとした。目の前にコーちゃんはいるのに、コーちゃんに首を絞められたのかとおもった。キュッと。くるしい。そんなわけはない。コーちゃんは私の前で、眉を下げて笑っている。ねえわたしやっぱりしんだほうがいい?
「それにキミは今とってもかわいいけど、この先何十年後かはしわしわでよぼよぼのおばあちゃんになるし。生きてるから」
「……やだ」
「でももうボクはすでにおじさんだよ。体もボロボロ、おじさん越えておじいちゃんに片足突っ込んでるかも」
コーちゃんが一度立ち上がって、私のすぐ傍までやってくる。傍まできて、私を抱きしめる。ギュッ、ではなくて、そっと腕を回して、背中をぽんぽんと叩くような、ひどくやさしいものだ。すぐ傍で聞こえるコーちゃんの声は穏やかで優しい。ホストの営業中に聞いてたような声とはまた違う。二人きりの時間でしかきかないようなもの。
「キミは生きてるから、おばあちゃんにもなるし、ボクと喧嘩もするんだよ、この先。嫌いになっちゃうかもしれないような大喧嘩もね」
「いやだよ」
「何回も何回も喧嘩して一緒におじいちゃんとおばあちゃんになってよ。こんな体のボクが『長生きしようよ』とかあんまり言えないけど」
「やだ」
「死んだあの子にはできないことじゃないか」
これ、嫌な言い方だね、ってコーちゃんが小さい声で呟いた。ごめんね、とも言った。私に言ったのかは分からないけど、謝っていた。ごめんね。ごめん。そんなふうに言わせてごめん。私がわるい。
「ボクと生きてよ。しなないで。おねがい」
静かな声でそうコーちゃんが口にした。私はほとんど無意識に腕を回してコーちゃんのことを抱きしめ返していた。こちらは、ギュッと、力強く。抱きしめて気付く。コーちゃんの肩ってこんなに頼りなく、小さかったっけ。ひどく弱々しい存在に思えてしまった。不思議だ。なんでも一人で背負ってきたような、つよい人なのに。
ずるいかな。私ずるいよな。あの子からしたら。いや、でも、ずるいなんて思わないのかな。あの子はべつに、コーちゃんを独り占めしたかったわけではきっとなくて。じゃあやきもちなんかやかないのかな。私のこれは、なんなんだろうな。
ぼんやり考えながら、抱きしめる力を強めた。こんな、答えのないことをずっと考えることができてしまう。死んだ人に対する勝手な想像や押し付けもできてしまう。ずるい。生きてるって、ずるいかも、結構、かなり。
「生きてる人間には敵わない」と、死んだ人間だって思っているのかもしれない。だっていくらでも思い出は増えるし、しわしわよぼよぼだっていいよって言われてこの先もっと好きになってもらえるし。きっとずるい。かなわない。「生きてる人間には、かなわない」。――私はその言葉を聞いたことがない。まだ生きているから、もうしばらく聞けない。私はコーちゃんとくっついて、抱きしめあって、その心臓の音を聴く。吐息に耳を澄ませる。よわよわしい音。ああ私たちって、まだ生きてる。