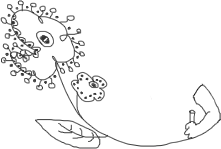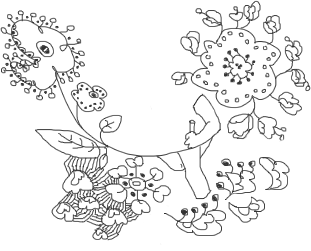「足立さん、最初の頃ははしゃいでくれてたじゃないですか。すっごい大袈裟にデカい声出して『えぇ~!?僕の誕生日、覚えててくれたんだ!?』って。忘れもしませんよ。マスオさんもビックリな『えぇ~!?』でしたよ」
「え~?内心『こっわ!』って思ってたよ。誕生日教えた覚えなかったし」
「教えましたよ。聞いたら答えましたよ。『えぇ~?なになに?聞いたからにはプレゼント期待しちゃおっかな~?アハハ、なーんて』って言ってましたよ」
「社交辞令みたいなもんじゃない?そういう会話の流れって。っていうか君、過去の会話いちいち覚えててこっわいねぇ~!」
「一番最初、初めてあげた誕生日プレゼントなんだか覚えてます?」
「えっ!覚えてない」
「あ、はーい。いいでーす結構でーす」
「はいはい嘘嘘。覚えてるよ。アレでしょ。ちょっとイイ感じのマフラー」
「それ二年目ですね」
そりゃあ、最初の頃はそういう演技だってするよ。へらへら笑って頭の後ろ掻いて、いやあ参ったなあ~なんて照れて嬉しがるフリだってする。だって、君もそう思ってたじゃない。あの頃は。「足立透」はそういう人間だって、勝手にそう思ってたでしょ。そういう、君の思う通りに、イメージ崩さないように、演じてあげてたんだから。感謝してほしいよ。嬉しかったでしょ、君だって。もじもじちょっと照れて俯いてたじゃない?「いえ、本当につまらないものですが……本当に、期待はせずに受け取ってください……」なんてか細い声でさ。
「足立さんだって覚えてるじゃないですか。過去のこと。いちいち」
「うるさいな。君があんまり可哀想なくらい真っ赤になってたから忘れようにも忘れられないんだっつの。ふきだすの我慢してこっちは大変だったんだよ?……ぶっ!アハハ!なんか今笑えてきた思い出して」
「なんでそこまで覚えてて渡したプレゼントは覚えてないんですか?」
「えぇ?ホントにマフラーじゃないの?ごーめん、ほんっとに分かんない。マフラーの年もおんなじように君の顔真っ赤だったんじゃない?これ二年目の記憶?」
「変わっちゃいましたね、足立さん」
「君もね。あの頃の初々しさもう微塵も残ってないじゃない」
そうだよ。いつからだったかな。何年目からだったかな。もうだんだん、取り繕うのも面倒になってさ。隠さなくなってきたんだ、いつの間にか。
ああ今相手すんのめんどくさいなあ、ちょっと鬱陶しいなあ。そう思ってるのを隠さず表に出すようになってしまったらしい。最初、君はちょっと傷付いた顔をしていたのかもしれない。ショックを受けて。そんなの知ったこっちゃなかったけど。
イメージと違う、そんな人だと思わなかった……とはべつに言われなかったけど、きっとそう思ったことだろう。まあ、けどこっちだってさ、そう思われてもいいやって思ったんだ。君が離れていったところでさ、べつに、どうだっていいやって。
「あのさ、もういいんじゃない?無理に続けなくても」
何が?って顔をしてこっちを見る。「続ける続けないの問題じゃなくないですか?二月一日は一年に一回必ずめぐってくるものですよ」あーあ、可愛げのない台詞。面白味も無い。何を言いたいかなんて、わかってるくせにさ。
「君だってさ、べつに俺じゃなくていいんだろ。もう好きなんかじゃないくせに、惰性と意地で続けてるだけ」
最初は、たしかに、まあ好きだったんじゃない?でも、蓋を開けてみれば、君が思ってる「足立透」なんて男とはずいぶん違う、こういう中身だったわけで。もう君の、理想の?君の好きになった「足立透」でいてあげることは難しい。だって疲れるしバカバカしい。なんの得も無いのに、そんなの演じてやらないといけないなんて。
僕の本性ってやつを見て、勝手にガッカリして離れていくと思ったのに、君はそうしなかった。そうしないまま、結局こんなに時間が経った。もう離れるタイミングを逃して、意地になっちゃってるだけなんだよ。時間を無駄にしてるだけなんだよ、お互いに。もう分かってるじゃない、お互いにさ。君だって最初の頃より随分と、僕に向ける眼差しの種類は変わったでしょ。ちょっと扱い雑になって来てるじゃん。それもまたムカつくんだよなあ。生意気で。君っていっつも、まあ二月一日周辺は特に、押しつけがましくって面倒で。本当に、僕はずっと前から君のことが、
「……泣かないでよ。慰めなきゃいけなくなるじゃん」
唇を噛んで、堪えていたらしいけど結局彼女のその目からぽろっと大粒の涙が零れる。それを、どういう感情で眺めていればいいのか分からなかった。ただ、「ああ君でも泣くんだな」とは思った。今までどんな嫌味や意地悪を言ってもそんなふうに泣かなかったくせに。泣いて逃げていってくれなかったくせに。今日くらいは、まあ、最後くらいは、泣いてもいいやと彼女の涙腺も空気を読んでくれたんだろうか。いいね、お別れっぽくなった。
唇を震わせて、でも無理に調子を整えるように息を吸い込む。次に相手が吐き出す台詞に、耳を澄ませた。なのに。
「たしかに最初の頃とは違う気持ちかもしれない。足立さんのことを知りすぎたせいで。でも、最初の頃と違うからって、私のこれが好きか好きじゃないかなんてそんなの、なんで足立さんに決めつけられないといけないんですか」
泣いてる人間にしてはやけにハッキリきっぱりと、いっそ怒りすら滲ませるような声でそう言った。なんでだよ。そういう流れじゃないだろ。今聞きたいのは、別れの、最後の言葉であって。
俺の顔を睨み付けながら泣いてる女の顔を、呆然と見つめた。
「なんで『好きじゃないくせに』とか言うんですか」
「好きじゃなかったら、いま涙なんか出てない」
「好きじゃなきゃ、足立さんにそんなこと言われて、こんなに悲しくなってない!」
語尾を強めて、それが合図みたいに言い切った途端にぶわっと泣き出した。ああ、うわあ、めんどくさ。目の前でわーわー喚く女を、眉間にしわ寄せて睨む。ああもう、あーあ。
「……今度こそ離れていくと思ったんだけどなー」
呟いて、溜息吐きながら頭の後ろをがしがし掻いた。小さな狭い部屋のまんなかで、僕らは向き合って話していた。
年が明けたかと思えばあっという間に一月が終わって、今日、昨日より少し気温が高くそれでもじんわり普通に寒い、二月一日。覚えやすい日付だけど、その日を特別に思うことなんてなかった。誰かさんが毎年毎年騒ぎやしなかったら、意味なんてもたなかったんだ。
いい迷惑だよ。「誰かさん」は、今目の前でぐすぐす鼻をすすっているけど。
「あのさぁ……僕は親切で言ったんだよ。君が無駄に心を痛めないように、気を遣って僕の方から言ってやったわけ。今日だけじゃないし、今年だけじゃない。何度も、離れてくチャンスはあげたんだよ、今まで。なのに君ってばさぁ……」
ほんと空気読めない女だな、救いようがない。ホント、どうしようもない。
話の雲行きと僕の台詞を不思議に思ったのか、彼女が鼻を啜りつつも僕の顔を見ようと顔を上げた。いや上げようとしたので、僕はそれを阻止するように、手のひらを思いっきりガッ、と相手の頭に乗せた。押さえつけるように力を入れて、ぐりぐりわしわし、乱暴に髪を撫でる。あだちさん、と掠れた声が耳に届く。けど顔を上げてこっちを見ることは許さなかった。
「覚えてるよ。初めてもらったプレゼントは靴下だった。なんかあったかい素材のやつ。去年穴あいたから捨てたけど」
僕に強制的に頭を下げさせられている彼女が、僕の手のひらの下で小さく何か言った。「え?」とか「はい?」とかそんな一言だったと思うから無視した。
「二年目がマフラーで三年目がネクタイだ。覚えてるよ。覚えてるんだよ、こっちだってさ」
忘れようと思ったって覚えてるんだ。この季節になると嫌でも思い出すんだ、過去の二月一日を。マフラーもネクタイも部屋のどっかに転がってて、でも確かにそこにあるから、生活や日常の一部に、僕の過去に、人生に、君がいるんだと思い知らされて、本当にいい迷惑だ。靴下はもう無いけど。君が寄越した余計な言葉も、感情も、何度振り払おうとしても消えてくれない。
「これだけ言ってもやめない君が悪いよねぇ。知らないよ?僕は」
「え、っとぉ……」
「君はなんで僕のこと好きなの?幸せになんかなれないと思うけど。する気もないし。でもそれでいいってこと?」
少し驚いたような目玉がこっちを見た。そこでやっと、彼女の頭を押さえつけるのを自分の手がやめていることに気付いた。僕の顔を、まじまじと、珍しいものを見るような目で覗き込む。それがなんだか無性にうざくて、僕は顔を顰めた。
「なに?」
「いや、え、つまり足立さん、自分といても幸せになれないと思うからって理由でわざと女を突き放してあげるような優しさが……あったんですか…?」
「はあ」
「あ、足立さんにそんな優しさ、要らなくないですか……」
「はあ?」
「はあ」
「無いよ」
「ないの?」
「無くなったよ、今日、たった今ね」
こちらの目を覗き込んでいたその顔がうざったくて、片手で彼女の両頬を無理矢理掴んでやる。ぐっと力をこめれば、多少逃げようと頭を振る抵抗は見せたけど、意地でも離してやんなかった。もういい。もうわかった。離してやるもんか。
「お前みたいなムカつく女、手の届かないところで勝手に幸せになんてさせてたまるか。せいぜい一生俺から離れらんなくて苦しめよ。バーカ」
たっぷりの皮肉を込めて、渾身の「バーカ」を吐き捨ててやった。初めて会った頃の、「へらへら演じてやってる僕」しか知らないコイツが聞いたらどんな顔するかな。けど今のコイツはもう知ってるから、もう全部分かった上で離れていかない馬鹿な女だから、一瞬目を丸くしたあとに、口元をにやつかせた。顎を掴んでいるこの手に、彼女の頬の筋肉が動く感触が伝わるくらい、はっきりと笑う。あーあ、救いようないなぁ、本当に。
「足立さんと幸せになりたいわけでも不幸になりたいわけでもないです。ただ、一人にしたくないなぁとは、おもってる」
そんなことを口にして、彼女はケーキをフォークでつついていた。ふうん、と興味のない相槌を打つ。僕も自分の分のケーキをつついていた。ああ、いつも通りの二月一日だ。余計な言葉と、要らないプレゼントが増えていく。
「来年は何くれるの」
顔を上げずにそう口にした。顔を上げなくても相手が少し驚いた表情を浮かべたことが、なんとなくわかった。
「だって君ってば僕のこと大好きじゃない?どうせ来年も押しかけに来るんでしょ?」
「……足立さんって実は結構私のこと好きなの?」
「いやぁ~好きじゃないけど?」
だってさ、君っていっつも、二月一日周辺は特に、押しつけがましくって面倒で。離れればいいのに離れていかなくて、好きでいるのやめればいいのにやめなくて、そのくせ勝手に泣いて勝手に怒って、本当に、僕はずっと前から君のことが、