|
クラスでいちばん人気の男の子が、私に向かってそう言った。勉強もスポーツも出来て、他の男子よりずっと大人びていて、確かに彼はとってもかっこいい男の子だ。母親を亡くしている過去があって、それを知ってる女子は特に「笑顔にたまに暗い影がある気がして」だのなんだのと、彼を儚げで寂しがりで愛を求めてる人扱いして騒いでいる。私が月光館学園に入ったのは中等部からなので、彼の過去を知ったのはつい最近だ。初等部からの付き合いの人ならほとんど知っていることらしいけど。そんな彼、天田くんと私の接点といったらただクラスメイトというだけで、何か特別な関係を結んでいるわけじゃない。だけど、不思議なことに一個だけ、他の女子にはなく私にはある「特別」が、私と彼の間には存在していた。 「、信じてないでしょ」 苦笑いする彼に、相槌も打たず、その表情をぼんやり見つめる。耳の奥で何度も反響する「」という、私の名前。それが、私達の間の「特別」だった。天田くんは、私のことを「」と呼ぶ。他の女子のことはそんなふうに呼ばない。苗字で、さん付けしたりする。だけど私のことは、違っていた。私の名前を一目見たとき、彼はまあるい目をもっとまあるくして、それから、小さく「いい名前だね」と呟くと、微笑んで私に告げたのだ。「下の名前で呼んでもいいかな」って。あの時のことは忘れない。周囲のクラスメイトのどよめきと、彼の恐ろしいくらいに綺麗な微笑。優しい笑みなんかじゃなかった。あれはきっと、悲しい瞳だった。彼のことを好きな女の子たちの言う「暗い影のある笑顔」とは、あれのことを言うんだろうか。 「…信じるとか信じないじゃないよ。少しびっくりしただけ」 「それもそうか。いきなりこんなこと言うなんて、頭でも打ったのかって思われちゃうよなぁ」 「べつに、天田くんを疑うわけじゃないけど。ちょっと突飛な話だね」 天田くんは頭も良くて運動も出来て先生からも生徒からも好かれていて優等生だけど、たまにおかしなことを言う。今だってそうだ。いきなり「小学生の時に世界を救ったことがある」なんて言われて、気の利いたリアクションなんか私が取れるわけない。だけど天田くんは嫌な顔ひとつせずに笑って、さらに話しだす。まるで子供が大人に向けて特撮ヒーローのかっこよさを説明するみたいに、楽しそうに、誇らしそうに。 「は会ったことないと思うけど、当時高等部に凄い先輩たちがいたんだ。かっこよくって僕の憧れだった人たちでさ。その人達と、深夜の0時になると現れる化け物と夜な夜な戦ってた。…あ、素手じゃなくて、僕らにだけ使える特別な力があって、それで戦うんだ」 化け物だの、特別な力だの、少しの照れもなく大真面目に話す天田くんの表情を、ぽかんと眺める。イキイキと話すその様子を見てると、「何いってるの」とか言える雰囲気じゃなかった。たまに、本当に、おかしなことを言う。周りの大人もクラスメイトも気づいていないようだけれど、私は知っていた。きらきらと王子様みたいに微笑む彼がたまに、酷く濁った暗い瞳で、どこか違う世界を見ているのを。私達とは違うどこかで生きていることを。私はその世界から彼を引き上げる術を知らなかった。ただ沈んでいく彼を眺めるのだ。もしかしたらこの「おかしなこと」は、私にしか話していないのかもしれない。確証なんかないけれど、なぜだかそう思えた。 「それで、その戦う僕らの中にも、リーダーがいたんだ。誰より強い女の人だった」 そこで一度天田くんは言葉を区切った。それまでぺらぺらと話していたというのに、何かに引っかかったみたいに、続く言葉が出てこない。話し終わったんだろうか、と思ったけれど、そうではないらしい。「誰より先頭に立って」ぽつりと、天田くんの声が床に吸い込まれる。「誰より多く敵を倒して」「それから」「それから」 「本当に、凄い人だったんだ。強くて、明るくて、堂々としていて。女の人なのに、いつも僕らを守るんだ。守りたいと思っても、気づくといつも、こっちが守られているような、そんな人だったんだ」 声が震えている、と思ったのは、気のせいじゃなかった。天田くんが、きゅ、と拳を握ったままに、「ずるい人だ」と、無理に口元だけで笑った。それを見て、私は急に、この場から逃げてしまいたくなる。言っている意味の半分も理解できないのに、彼の言葉を聞いていると、胸に矢でも槍でも刺さったように、苦しさがこみ上げた。もう天田くんは、私のことなんて見ていない。痛いくらい握りしめた自分の拳を見つめて、呻くように言う。 「僕にはこれっぽっちも守らせてくれなかった。僕はずっと、彼女を守りたかったのに」 その声に堪え切れなくなって、気づくと私は「天田くん、」と名前を呼んでいた。だけどやっぱり彼はこちらを見ようとしない。自分の無力さを呪うように、唇を噛んで、立ち尽くしていた。やがてゆっくり拳を開いて、なんにも無い、からっぽの手のひらを冷たい瞳で見下ろす。その手ですくえなかった何かを見つめるように、じっと、無言で。声を掛けるべきか否か、私はただただ考えることしか出来ない。声を掛けるといっても、今、私が何を言えるんだろう。天田くんが先ほどから話す内容はきっと私に全然関係のないことで、私が分かってあげられるはずのない過去のことだ。 「」 私に出来ることは何もない、と遠巻きに見守っていたところに、急に名前を呼ばれてビクリと肩が跳ねた。顔を上げた天田くんと目が合う。浮かべる表情は、いつもの微笑だった。何故か今は、その表情が怖い。「僕、小学生の時に、」また同じ話を繰り返すのかと思って背筋が凍った。だけど、その続きは先ほどとは違う。初めて耳にする言葉だった。 「君と同じ名前をした女の人を、好きだったんだ」 その一言に、雷に打たれたような衝撃がびりびりと全身を駆け巡った。目の前の光景が一瞬、遥か彼方に遠ざかる。全てに合点がいく。天田くんが守りたかったもの。守れなかったもの。私の名前。守らせてくれなかった人。私は足が縫い付けられたみたいに、その場から動けなくなる。そんな私を見透かしてるように、天田くんは一歩、私に近づいた。「は」と、彼が口にする自分の名前すら、名前以上の何かが伸し掛かっているように聞こえる。 「は、いなくならないで」 その言葉は、同い年のクラスメイトの言う言葉なんかじゃなかった。もっと年下の、そう、小学生くらいの男の子が、口にするようなそれに聞こえた。天田くんの手のひらが伸びてきて、私の肩に触れる。そのまま引き寄せられて、気づけばそっと抱きしめられていた。男の子に抱きしめられるのなんて初めてなのに、ときめきなんかよりも、こみあげてくる切なさに似た悲しい気持ちが勝る。怖いと思った。このままじゃ、ただただ悲しいだけだと思った。私は震える唇で、やんわりと、彼を拒絶する。 「天田くん、私は、さんじゃないよ」 口にすると、なんだか泣きそうになる。顔も知らない誰かが、私と一緒に悲しんでくれている気がした。だけど天田くんは、驚く素振りもなく、私の髪を撫でながら笑った。「ばかだなあ、分かってるよ。それくらい」 「は、さんとは違う。僕より背も小さくて、僕より非力な女の子だ。だから、今度こそ、僕が守ることができる。だから、だから…僕が、守るよ、」 ちがう、ちがうよ天田くん、分かってない。私はさんとはちがう。あなたが守れなかったさんじゃない。あなたが守りたかったさんじゃない。あなたが守りたいのは、なんかじゃない。伝えたい言葉が、声に出すより先に消えていく。きっと伝わらない。伝えることができない。私は唇を噛んで、彼の腕の中で静かに涙を流した。愛しい人を抱きしめることの出来なかった小さな腕が、私を捕らえて離さない。 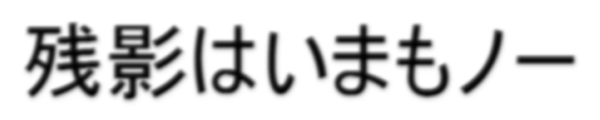 |