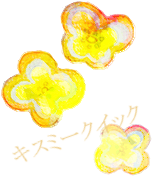
「凛!はい、これ!お土産!」
ぺかぺかと光る上機嫌な笑顔で、大きな四角い箱を差し出してきたが気に入らなくてしょうがない。幸せそうな顔をして、俺の部屋にずかずかと入り込み、ぺたりと床に座って、紙袋からそれを出し、渡す。その一連の動きを、俺は黙って睨む。だというのに、の上機嫌は少しも傾くこと無く、笑顔だ。まるで「凛もおんなじ気持ちになってくれるでしょう?」と暗に期待されているようで、俺はプイと顔を逸らす。何がそんなに嬉しいのか、はにこにこしたまま、「どうしたの?」と訊くだけだ。
「これね、お菓子だよ!おいしいんだって!動物の絵が描いてあるの!」
「……」
「あ、でもこれ凛だけにっていうわけじゃなくて、家族みんなで食べてね!」
「……」
「じゃーん!凛にはお菓子以外も用意してあるのでしたー!ほらこれ、ストラップね、ご当地限定って書いてあったから!かわいー?」
「ぶっさー」
「ええ!?」
上機嫌で話していたがそこでようやくショックを受けた顔になる。俺は相変わらず、寝転がって、片方の肘をついて、を見ていた。きっと誰から見てもふてぶてしい態度。だってしょうがない。の機嫌が良いから、俺の機嫌が悪くなるんだ。ただそれだけ。は、よく分からない変な生き物がぶら下がった黄色いストラップを行き場なさげに手の中で弄んで、俺の顔とそれを交互に見た。困惑しきったように、不安そうに俺の顔を見る。その表情を見ているとなんだか余計に、困らせてやろうという気が起きてしまうから我ながらタチが悪い。はあ、と溜息を吐く。しばらくの沈黙。髪の毛先をいじくりながら、から目を逸らして鼻を鳴らした。
「旅行の土産なんて欲しくない。食い物なんかどうでもいいしやー」
「じゃ、じゃあ、こっちのストラップだけでもつけてよ…せっかく買ってきたのに」
しゅんとした声に、ほんの少し拗ねたような声も混ざる。ようやく、俺の機嫌が悪いことと、自分との温度差に気が引けてきたらしい。それでいいんだよ、と内心だけで呟くと、俺はからストラップを毟り取るように受け取った。指で適当につついたあと、顔を上げる。が少しぎくりと肩を揺らした。べつにコイツをいじめるいじめないに関わらず、このストラップはどこも可愛くないけど。(そういえばこいつ、ぶっさいくなあぐーを可愛い可愛いと騒いだり、変な顔したクマのぬいぐるみを好き好んで大量に集めていたりしていた。センス無さすぎ)
「…凛、どうして機嫌悪いの?」
「やーが機嫌いいからよー」
「なにそれ…どうして私の機嫌いいと凛の機嫌悪くなるの?今までそんなことあったっけ」
「わんの機嫌が悪いのに、やーがへらへらしてるのが気にいらないんばーよ」
「……それって凛は最初から機嫌悪かったってこと?でも私が機嫌良いから機嫌悪くなったんだから…えーと…凛が機嫌悪いのは私が機嫌いいからで、でも機嫌が悪い時に私が機嫌良かったから機嫌悪くなった?え?」
最近テレビで見た「鶏が先か、卵が先か」という話を思い出した。けど現在の俺達の状況はそんな難しそうな話とは程遠い。しかしは数学の教科書の仕上げ問題を解くときみたいなむずかしい顔をして、考え込んでいる。馬鹿だ。俺はその馬鹿さに呆れつつ、未だ少し、機嫌が悪い。床に、正座を崩したような女特有の座り方で座っているを、寝転んでいる俺は必然的に見上げる形になる。じ、と見つめて、考えた。いつものだ、と。今着ている服は、彼女のお気に入りのもので俺は前にも見た覚えがあるし、今座っている位置は俺の部屋にやってきたときの定位置だ。帰る頃になったら「足痺れた〜」と情けない声を出すだろうから、俺は意地悪くその足の裏をつついてやったりする。いつも、だ。当たり前の光景。ここ一週間くらい、見なかった光景。――あ〜気に入らない!
「嬉しそうに土産渡して、嬉しそうに旅行の土産話して、嬉しそうにわんに『ただいま』なんて言って、ムカつく」
胸の内で留めておくつもりが、気づいたときには声に出していた。俺の呟きを耳にしたは、それまで必死に俺の機嫌が悪い理由を知りたがっていたから、思ってもみなかったタイミングで答えが降ってきたことに拍子抜けしているようだった。そしてその答えが分かっても意味が解らないようで、変な顔しながら首をひねっている。俺が不貞腐れている様子に、はっとしたようにが慌て始めた。
「え、だ、だって、旅行楽しかったし、凛にも伝えたくていろいろお土産話を…」
「たーが聞きたいなんて言ったさあ」
「! な、だって、だって凛が…嫌がるなんて思わなかったし…」
声がだんだんと小さくなっていって、じわじわとの表情が歪んでいくのが分かる。あー、泣く。泣くぞ、これは。特に驚きもせずを眺める。めそめそぐすぐす泣き出すを想像していたっていうのに、ヤツはぷつんと何かが切れたように大声でわめきだした。「喜んでほしかっただけだもん!知らないよもう!凛のバカ!ハゲろ!」……家中に聞かれてそうで焦る。いや、焦る以前に、こっちこそカチンときた。「はあ!?」と思わず横になってた体を起こして、負けじと大声を出していた。
「やーが楽しい思いしてる間、わんがどれだけ、……、……」
やめた。言葉を早々に切り上げると、が動きを止めて、ぽかんと馬鹿みたいに間抜けな顔をした。俺ががしがしと頭の後ろを掻いて、疲れたような大きい溜息を吐くと、ようやくの口が動く。
「さみしかった…の?」
おそるおそる聞いているくせに、表情がちょっと嬉しそうなのがムカつく。手首の骨の辺りを使ってゴッとの額を軽く殴ると、そのまま後ろに大きくのけぞった。殴るというよりは「押した」だけだ。(「痛い!」「痛くやってねーがよ!」)額をおさえて文句を言うを睨んでフンと鼻を鳴らしてから、俺はまたごろんと横になった。目を瞑って、の顔なんか見ずに、ぶつぶつと文句を言う。それすらにやにや笑いながら聞いていそうでムカつく。
「大体、わんの居ない場所でやーが楽しいとか嬉しいとか、そーいうのが、気に入らないんばぁよ」
「…どうして?」
「わんが隣にいないのに、楽しいとか」
「いやなの?」
「わんは全っ然楽しくなかったさぁ!…が傍にいなくて、全っ然」
それなのに。いつもどおりのが、「あーたのしかった!」って顔しながら俺の前に現れやがった。それがひどく気に入らない。すごく、気に入らない。…知り合いに聞かれたら、からかわれたっておかしくないその言い分に頭を掻いた。こんなの、俺だって他人の口から聞いたらそいつをからかっているだろう。子どもだなって、バカだなって、みっともないなって。それらの言葉が今は全部自分に跳ね返ってきて、無性になんか、むしゃくしゃしてきた。そういえばの反応が無いな、と顔をそっちに向けようとした直後、背中に思い切り誰かの体重が乗っかってきて、カエルが潰れたような声が口から漏れる。
「ぬぅーやが!」
「だって凛が!勝手過ぎる…」
寝転んでいた俺の背中に乗っかってきたかと思うと、そんなことを泣きそうな声で呟く。…とりあえず、こんな体勢じゃ、の顔なんか見えやしない。体をひねって寝返りを打とうとすると、も腰を浮かせてそれを促した。結局、俺が仰向けに寝転んで、その上にという、なんとも男にしてはむずがゆい体勢が出来上がった。女に押し倒されたような感じ。こんなふうに見下ろされる趣味は無い。改めて顔を突き合わせると、さっきまでのやり取りを思い返して妙に気恥ずかしい。だがは俺の腹に手をついて、じぃ、と俺の顔を見つめ続ける。もう一度、なにすんだよと呟けば、がきゅ、と唇を噛み、俺の服を握った。何かを堪えるみたいな表情。まばたきの度に揺れる睫毛や、男の自分に比べてぷっくりしてる下唇、赤みを帯びてく頬が、のくせに色っぽく感じさせるから、むかつく。自分の余裕がなくなっていくことにも、むかつく。
「凛が、そんなふうに思ってくれてるなんて確かに分からなかったけど、でも私…私だって、凛のこと考えてたよ。いっぱいいっぱい考えてた。こっちに帰ってきた時だって、凛に会えるって思ったら、話したいこととか、言いたいこととか、いろいろ考えてたら自然と、そりゃあ、だらしない…笑顔になってたかもしれないけど…」
一週間ぶりに再会して、あんなにも上機嫌で馬鹿みたいに笑顔だったのは、旅行が楽しかったからじゃなくて、俺に会えたから。会えなかった分を埋めるように、たくさんたくさん話したいことがあったから。頬を染めて、一言一言を大事そうにそう告げる。その間ずっと、一時も取りこぼさず好きなだけ、見つめることができた。ああこいつは俺のことを考えるだけでそんな表情が出来るのか。(可愛いじゃんか、なんて…口が裂けない限り言ってやらない)手を伸ばして、の頬に触れる。俺を見下ろす瞳が、少し戸惑うように揺れた。
「やー、わんに会えなくてそんなに寂しかったばあ?」
「り…凛こそ、寂しいって言ったじゃん」
「わんがいつ寂しいなんて言ったんやっしー」
「え、…ええ!?」
「やーが居ないと、からかう相手がいなくて暇だっただけさー」
え、え?と驚き慌て出すを見て、俺は大口開けて笑い出す。頬をふくらませ、むっとしたが俺を叩いてやろうと手を振り上げたので、それより先に腕を回して抱き寄せる。簡単に、すんなりと、腕にの頭がおさまる。さっきまで怒ってたくせに、俺の胸に押し付けられたまま、が笑った。柔らかい髪をぐしゃぐしゃと乱暴に撫でてやる。ああそうだ、寂しくなんかなかったさ。ただ、お前がいないとちょっとつまんなかったってだけ。旅行先で変な男に絡まれてないかなってちょっと心配してやっただけ。早く帰ってこねーかなって、毎日毎日思ってただけ。
「ねえ、凛」
俺の胸から顔を上げたが、瞳をじっと見つめてくる。ただでさえ近い距離なのに、ずい、と顔を近づけてきたので、こちらも相手の頭の後ろに腕を回して引き寄せる。唇を重ねて、離して、が何か言おうと唇を震わせた直後にもう一度重ねた。は、と一つ息を吐いて、それから彼女が笑う。「『ただいま』って、言おうとしただけなのに」嘘つけよ。俺は「キスして」って言ってる顔にしか見えなかった。