|
「あ!やばっ、もう待ってるかも。ごめん、急ご!日向くん」 職員室から戻ろうとした時、カントクがふいに声を上げた。今度の日曜の体育館の使用時間について顧問に確認を取りに、部活の後二人で職員室へ行った帰り。そのまま昇降口へ向かわずに、一度体育館の方へ戻らなきゃいけない。俺にもカントクにも、「一緒に帰ろう」と言って待ってる人間がいるからだ。カントクのその相手ってのが、「」なんだけど。足を速めた彼女に続いて廊下を歩きながら、ぼんやりと、あいつ。の顔を思い浮かべた。自分と同い年の、んでもって同じ中学出身の、ごくごく普通の女子。だいたいいつも、校門の近くか体育館の出口でカントクが出てくるのを待ってる。あまり親しく話した記憶は無いが、カントクと話しているときのは大体が笑顔なので、俺の脳裏に浮かぶの表情も柔らかいものだった。 「ってなんか部活入ってんだっけ?」 「え??」 「や、いっつもバスケ部終わるまで待ってんなーと思って」 「ああ、あの子ねえ、先帰っていいって言ってるのにいっつも待ってるのよ」 「え、用もねえのに?自分も部活があって帰る時間被る、とかじゃなく?」 「そーよ」 まったくもう、とむくれてみせるカントクの声には、呆れは混じっていても、嫌悪の色は見られなかった。きっと本人にも「先帰っていいって言ったでしょ!」と怒るんだろうが、内心まんざらでもないに違いない。バスケ部の練習は下校時間ギリギリまで続けるし、この時期もう帰り道が真っ暗、なんて当たり前にある。そんな時間まで、は絶対にカントクを待ってる。そりゃ、男オンリーの部員の他に一緒に帰る女友達がいるのはいいことだし、カントク自身ちょっと嬉しがってる部分も、あるんだろうけど。なんとなく、のそこまでの執着に眉を寄せてしまう。 「一緒に帰るためだけに残ってんのって、すごくね?」 「すごい…のかしらね。なんかもー、当たり前になっちゃって!あ、でもホント私が待っててって言ってるわけじゃないのよ?」 「いや、だからが。別の友達と帰れば―……、あー…」 なんとなく、失言だったような気がして口を押さえる。視線を泳がせながら、ふと、考えたのだ。がカントク以外の「友達」と一緒にいるところを見たことがあっただろうか。きっと自分が思い出せないだけで、注意して見てないだけで、たくさんあるはず。あるはずなんだ。休み時間とか、女子同士固まって喋ってたりするだろ。…だが考えても考えても、その集団の中には必ずとカントクはセットで隣同士に座っていて、カントクの存在無しに一人が誰かと喋っているところが浮かばない。 「…、昔からカントクにべったりだよな」 ぽつりと呟いた言葉に、自分自身で大きく頷く。それに続いてカントクが「そーなのよね。私以外と帰るって選択肢が、無いわけじゃないのにさ」と、こまった娘を持つ親みたいに、やれやれと肩を竦めつつ、笑う。つられて笑おうとして、ふと、にとってそんな選択肢、「無い」んじゃないか?と思い至り、なんだか笑う気にならなかった。は前から、俺の知る限りずっと、カントクにくっついて歩いていた。中学の頃は大体、二人きりで行動していたし。今だって、授業や何やらで「二人組を作れ」と言われたら迷わずそこの二人は一緒に組むんだろう。高校になって、多少友達の幅は広がったように思えるけど、二人きりじゃなくなっただけで、二人が離れることは絶対に無い。 仲良いんだ。すげー、仲良い。(仲が、良すぎる) 「あ、リコー!今帰り?」 「日向君も一緒じゃん!」 「…ちーっす」 「そっちもお疲れー!こんな時間まで委員会?」 向こうから歩いてきた女子二人に声を掛けられ、カントクが笑顔で応じる。クラスの女子。カントクと仲良い。…そんでもってともたぶん仲の良い、女子。よく教室の一箇所に集まって喋ってる。まあ女子というのは数人集まっただけで独特の「女子」っていう空気を装備できるもんらしく、世間話でも始めそうな雰囲気に俺はそっと身を引く。なんか男が入るべきスペースじゃない気がしたからだ。 「日向くんと二人?二人で帰るの?二人っきり?」 「コラコラ。やめてよねー、その手の話でニヤニヤからかうの!」 わざとらしく小声でカントクに耳打ちしてるけど聞こえてるからな。本人ここにいるんだかんな。カントクが大袈裟に肩を竦めて手をパタパタ振るおかげで、かるーく流せているけれども。いや、なんか、それはそれで、微妙な気持ちになんだけど。居た堪れない。はあ、と溜息吐いたのとほぼ同じに、もう一人の女子が「そっか、リコは木吉くんだもんね」と楽しそうに耳打ちして、ぴくりと眉が上がる。バッと顔をそちらに向けて、「ちょっ!何言ってんのよ!?」と大きめの声を出したリコの赤い顔を視界の隅に入れて、もう一度溜息。今度は深く、深く。もやもやは息と一緒に吐き出されてはくれない。胸の端っこがちりちりする。そんな感覚。 「カントクー、俺先行くけど…」 「ちょ、ちょっと待って日向くん!…もーふたりとも、変なこと言わないでよね!?」 二人に釘を刺してさっさと俺のほうへ駆けてくるカントクに、小さく安堵するのと同時に、多少の悔しさも覚える。木吉の名前を出されて狼狽えるその顔は、どうやら俺の隣にはないらしい。俺には無いらしい、その表情。ぐっと眉を寄せて表情を強ばらせたのはほんの一瞬。背後から聞こえた声に、カントクがびくっと足を止めたから、俺ははっと我に返った。 「ほら、やっぱりリコはフツウじゃん」 「ね。やっぱ、だよね。ちょっとおかしいの」 やばい、と思った。なにがやばいのか、どうしてやばいのか、すぐには頭がついていかない。それでも直感で、そう思った。目を向ければ、カントクはすでに彼女たちのほうへ引き返している。「何が?」と表面上はいつもと変わらない声で、二人にそう訊く。二人は顔を見合わせて、ちょっと言葉を迷うように、だけど「だって、ねえ?」とでも目配せしあうように笑った。 「いや、ほら、ってリコにべったりじゃん?リコがいないとこだと、あたしらともあんまり喋んないんだよ?リコの友達だから仕方なくあたしらとも仲良くしてる感じするっていうかさあ」 「しかも本気で男に興味無いよね。リコのこと好き好き言ってさ、リコは好きな人とかちゃんといて、フツウだけどさ、冗談で言ってるって分かるんだけどさ、のアレってマジなんじゃないかなぁって、みんな陰で噂してんの」 「ねえ、ほんと気を付けたほうがいいんじゃないの?リコ」 申し訳程度に眉を下げているが、明らかに侮蔑を含んだその言い様と半笑い。俺のこの位置からは、二人のそんな表情しか見えない。カントクの背中の向こうに見える二人は、顔を見合わせて笑って、そのままカントクのほうへ視線を向けて、ぴたり、とおもしろいくらいに一瞬で笑うのをやめた。それだけで、分かる。俺からは後ろ姿しか見えないが、カントクが今、どんな表情を浮かべているのか、なんとなく。 「のこと、悪く言わないでちょうだい」 「え、で…でも、さ…ちょっとリコのこと好きすぎて怖いっていうか…」 「お…おかしいよ絶対!絶対ちょっと、あぶない子な気がする…」 「そんな子じゃないわよ!小さい頃から人見知りで、私以外に友達が作れなかっただけ。私はに好かれて嫌だなんて思ったことないし、私だってを大切な親友だと思ってる」 馬鹿にしないで。まるで、そんなおかしなことを疑うそっちがおかしいんだ、とでも言いたげに、強くはっきりした口調だった。本当にのことを友達として大切に思っていなければ、きっと口にできないセリフ。信頼。親愛。そういうものがこめられている。あんまりにも堂々として、真っ直ぐな彼女の言葉に、相手の二人も居心地悪そうにたじろぎ、「そっか、ごめん、冗談だよ」と無理矢理に笑って、その場を去っていった。ふう、と息を吐いて、俺の方を振り返ったとき、カントクは困ったように笑って、「ごめんね」と謝る。俺は一瞬返事が遅れて、「え、…ああ」と曖昧にちょっとだけ笑った。 「行こ!遅くなっちゃった。が待ってる」 その声は俺の足を引っ張って、気づけばまた小走りに廊下を進みだす。進みながら、俺の方は見ずに前だけを見て、彼女は言う。「、ほんっとに私の傍から離れないの。小さい頃からずうっとくっついてきて、真似っ子して。でも私にはそれが、もう当たり前になっちゃってる。もちろんにも」俺に話しているようで、自分に確認を取るような、そんな声だ。だから俺は相槌も打たずに、ただ足を動かす。「だから、初めてじゃないのよ。今回みたいなこと言われたの。その度、あの子なんにも言い返さないから、私がこうやって」そこまで聞いたところで、俺は気づくと頭を押さえていた。頭を抱えていた、というほうが正しいのかもしれない。頭痛がする。この、行き場のない気持ちはなんだろう。やりきれない気持ちは。「私が守らなきゃって、気ィ張っちゃってるのかもね」(そうじゃない、そうじゃないんだよ、)(お前は何かを間違えてる。だけどそれを俺はどうやったってうまく説明できないんだ) 「あんなに、いい子なのに。優しい子なのに。なんで誤解されるんだろ。レズだのなんだの、なんでみんなそんなくだらない陰口叩くのかしら。私達が仲良いと、気持ち悪く見えるの?」 のために怒りをあらわにする彼女は、の一番の親友だった。世界中が敵になろうとも、彼女はきっとたった一人でを守ろうとするだろう。何が起ころうとも、何を起こそうとも、無実を証明しようとするように。しかしどう考えても、彼女がを庇えば庇うほど、深く深く沈んでいく。波紋は大きくなっていく。そんな気がしてならない。なんでだ。なんにもおかしくないはずなのに、何もかもがおかしい気がした。とカントクを見ていると、何かがずれている気がしてならない。彼女は、他の誰よりのことを分かっているのに、他の誰よりを分かっていないんじゃないのか。 「あ、いたいた!やっぱりもう来てた。…隣にいるの、鉄平よね?二人で喋ってるなんて珍しい。…おーい!ー!鉄平ー!」 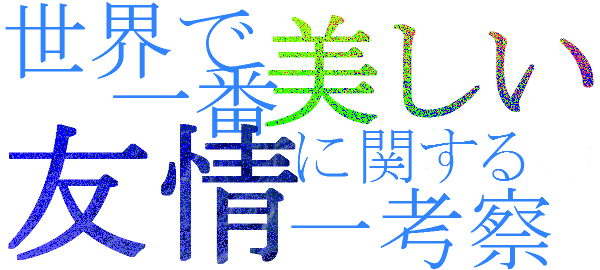 |